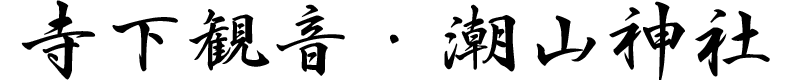仏教においての最終到達点は「悟り」を得ることで、この「悟り」とは迷いの世界を越え、真理を体得することです。
「仏」とは、悟りを開いた者である「仏陀(如来)」のことを指す言葉ですが、より広い意味で、悟りを開くために修行している「菩薩」や「明王」「護法善神」など、信仰の対象となる尊格を含めて「仏(仏尊)」と総称します。
「菩薩」の中でも良く知られている仏さまが観世音菩薩で、一般に「観音さま」と呼ばれています。
「般若心経(般若波羅蜜多心経)」の冒頭に登場する菩薩でもあり、「般若(修行の結果得られた、全ての物事や道理を明らかに見抜く深い智慧)」の象徴です。
観音さまは、死後の世界に於いて「しあわせ」を授けてくださるだけでなく、生きている現在の世界(現世)に於いても、人々に「しあわせ」を授けてくださる(現世利益)有難い「ほとけ」さまです。しかも、その功徳は、お願いすれば「すぐ」に現れるという速効性をもつために、古くから多くの人々に信仰されています。
「観世音」というのは、世の人々がいろいろな災難や苦悩を受けて救いを求め、一心に観世音の御名を唱える(一心称名)とき、その音(音声)を観て、直ちに助けてくださる(即日皆徳解脱)「ほとけ」さまなので、この名がつけられたのだそうです。
普通、音は耳で聴くものですが、観世音はこの音と観ずるのです。
「観ずる」というのは、よくよく「観察する」という意味で、救いを求める音声が、本当に真剣なものかどうか、単なる口先だけのものであるのかよくよく観察して、本当に真剣なものであれば、直ちに救いの手をさしのべて下さるというのです。
そのために、自分のお願いが、いかに真剣なものであるかを観世音によく観ていただくために、古くからいろいろな観音信仰の方法が考えられてきました。
七度詣、三十三度詣、百度詣りなどのほか、観音欲日と称して、各月毎に特定日を定め(寺下観音は毎月17日)、その日に観音詣りをすれば、多くの巧徳を得られるというものなどありますが、その中で最も観音巧徳の多いもの、霊験あらたかな信仰方法として三十三観音霊場巡礼にまさるものはないといわれてきました。